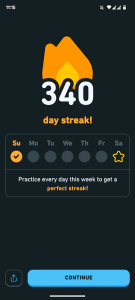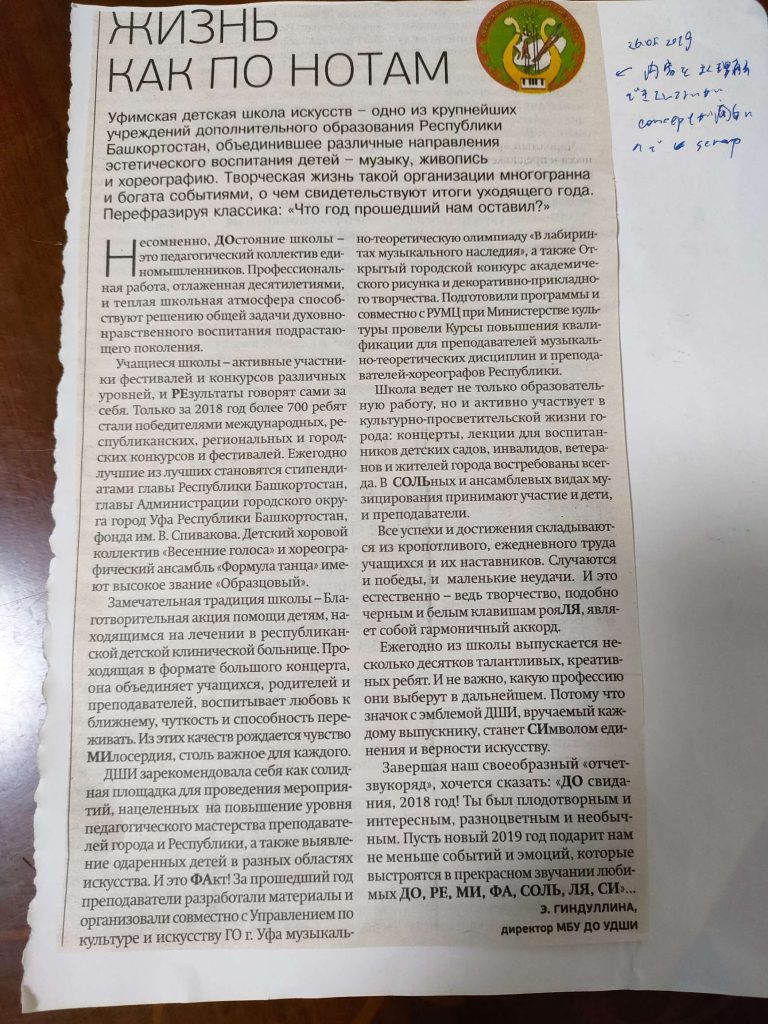外国語を勉強する時、心に取っておきたい言葉を今勉強している言葉で覚えてみることも役立つかもしれません。
例えば、ウクライナに住む友人が送ってくれたジャッキーチェン(Джеки Чан)の言葉。短いフレーズですので繰り返し練習することできっと覚えることができそうです。その結果、この言葉が自分自身をポジティブな気持ちにしてくれることはもちろんのこと、ロシア語の単語、単語の変化やリズムを学ぶことができると思います。この短いフレーズの中に込められた意味も噛みしめながら、ウクライナで戦争が行われている今の世界に住むからこそ一層この言葉の重みを感じることができるのではないでしょうか。
Джеки, доволен ли ты своей жизнью?
Знаете, я как-то услышал очень мудрые слова:
Твоя сложная работа – мечта каждого безработного.
Твой непослушный ребенок – мечта каждого бездетного.
Твой маленький дом – мечта каждого бездомного.
Твой небольшой капитал – мечта каждого должника.
Твое неважное здоровье – мечта каждого больного неизлечимой болезнью.
То, что Всевышний скрывает твои грехи от глаз людей – мечта каждого опозоренного своими грехами.
Твое спокойствие в сердце, твой спокойный сон, твоя доступная еда – мечта каждого, у кого в стране война.
Нужно ценить все, что у тебя есть. Ведь никто не знает, что произойдет с тобой завтра.
(日本語訳)
ジャッキー、あなたは自分の人生に満足していますか? (という問いに対してジャッキーチェンが以下のように答えました。)
以前にとても素晴らしい格言を聞いたことがあります:
あなたが抱えているやっかいな仕事は、仕事を失ってしまったすべての人にとっての夢。
あなたの言うことを聞かない子供は、子供を持てないすべての人にとっての夢。
あなたが持っている小さな家は、家すら無いすべてのホームレスにとっての夢。
あなたの持つわずかな資産は、負債を抱えているすべての人にとっての夢。
あなたにとって当たり前の健康は、不治の病にかかっているすべての病人にとっての夢。
あなたの罪を神様が他人の目から隠してくれるのは、自分の過ちによって恥ずかしい思いをしているすべての人にとっての夢。
あなたの心の平安、安らかな眠り、何でもない食事は、自分の住む国に戦争があるすべての人にとっての夢。
自分の持つものすべてに感謝しないと。明日、あなたに何が起こるかは誰にも分からないのだから。