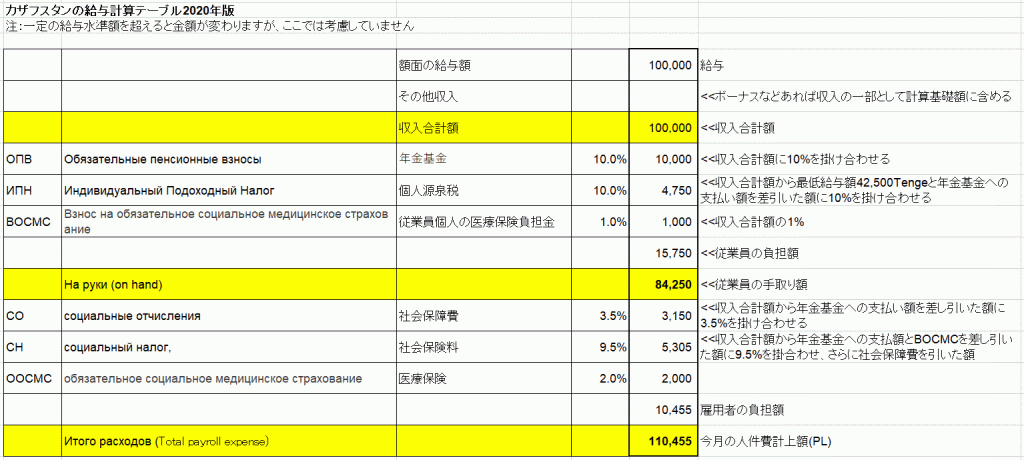日本に帰国してから早くも1か月が経過。生活のリズムも少しずつ慣れてきました。それにしてもこの雨、雨、雨。そして体にずっしりとくる湿気。モスクワの夏がどれほど快適であったかを感じています。身体が想像以上に疲れ、集中力が無くなってゆく。かといってずっとエアコンの元での生活は好きではない。適度にエアコンを使用しながらよいバランスを探しているところです。
そんな中、新しい職場で勤務し始めて約二週間が経過しました。
日本の生産性が低いといわれる所以の一つに、物事に明確な言い方を避けて、なるべく聞き手に察してもらうことを期待した会話の進め方、日本語の会話方法に問題があるのではないでしょうか。きっと多くの方がすでにこの点を指摘されているのでしょう、日増しにその思いは強くなっています。
何をしてもらいたいのか、その指示は分かるけれども、いつまでにやるべきか。具体的にどこまで掘り下げるべきか? たとえば、「締め切りはXX日までね」「了解。」その約束の期日の二日ほど前に「あれはまだできていないの?やっぱり早く欲しいんだよね」。あるいは、「この内容で関係者に依頼事項を出しておいてね。」その数日後には「やっぱりエクセルファイルを添付して、それに記入をお願いしたほうがよかったと思うんだよね…」
指示の仕方が悪い、そんなことを言うつもりはありません。「どのようなイメージのレポートが欲しいですか?」「なぜこのタイミングで急いでいるのですか?要求の背景にあることは何でしょうか?」そんな質問を部下の側からも上司にすることで、双方向のコミュニケーションとなり、そこで顕在化する課題や、新たに得られる情報が後々余分な労力と時間をセーブするのに役立つのではないでしょうか?あとは、上司の指示通りにではなく、自分自身でも深堀して考えてみる。自分なりにアレンジをしてみる。非常に多くの業務に忙殺されている中で、上司も人間ですから細かい指示、情報共有を一度で全てできないことだってあるはずです。部下から質問をしてゆくことで指示内容が洗練されて、より磨かれることだってあります。上司の責任は大きいですが、部下が上司をサポートする姿勢を自ら見せること、そうありたいと思います。ロシアで正社員が50人程の決して大きくない会社でしたが、部下を抱えながら指示を出している時に痛烈に自分の指示の限界、部下からの指摘の有難さを感じた経験があります。だからこそ、日本に帰ってきて自分自身が再び一社員として部下の立場になるときに、部下として上司のためにあるべき姿が分かったような気がしました。ロシアで、私の思っていたことと異なる結果が生じた時に部下に尋ねると「あなたの指示がこうだったから私はこうしたまでです。」という回答。振り返ればそれは決して否めないので私も部下を批判できないのですが、それでもやっぱり「ああしてくれていれば良かったのに…考えてくれなかったのかな…」という思いになったこと、ありました。
たとえばチーム内でもお互いにきっと直接言いたいことがあるのだろうけれども、黙っている。「ねえ、私の言いたいことは自分で悟ってね」という雰囲気。はっきりと物事を伝えることができればどんなに良いことか…?はっきりと伝えられない理由はおそらく、発言者の側にその言葉を発した時にその言葉が与える相手への強いインパクトを感じているから。そしてそれをなるべく避けたい。そうなると、短く話せばもっと分かりやすいのに、言葉を増やすと丁寧さの印象が増えるので言葉が多くしたくなる。言葉が多くなると一層伝わりにくくなる。相手の気持ちを考えるがゆえに言葉が増える。人格者でいることも — 決して悪いことではありませんが — 仕事を進める上では仕事の指示の理解を混乱させる要因となっているように感じます。丁寧にやろうとすればするほどにシンプルなものが複雑化するリスクをはらんでいる。面白くもあります。
会議では最後に「それでは何か質問ある方いらっしゃいますか?」…シーン…。「質問がないようなので、それでは終わります、ありがとうございました。」…しばらくして、会議に参加していた方々が立ち話をしています。「あの依頼事項は具体的には何を表しているんだろう?よく分からなかったんだよなぁ、わたしはこう思うんですよね…」一度となく会社で見る光景です。これも自分自身の質問が場の全員に関係の無いものだから他の人の時間をあえて取らないようにしよう、という気遣いに基づいているのだと思います。素晴らしいことだと思っています。一方で、意外にも自分の感じていることは他の多くの人も心の中で感じていることがあるのも事実かもしれません。そのような経験も一度ならずあります。そんなことも踏まえると、会議中に質問することこそが周りへの優しさでもあるのかもしれませんね。
仕事では、大切な特質である丁寧さが逆に機能してしまうことがある。
また、日本に戻ってきて、― 前から感じている点ですが ― ここでなぜ笑いが起こるの?と感じる場面が多々あります。なぜそこで笑うのか分からない、そして結論がうやむやになってしまう。振り返ると、あれっ、あの件って結果はどうなったんだけ?と。難しい課題になればなるほどに笑いが重要な役割を占めるのかもしれません、もしかするとはっきりとした結論が求められておらず、それはそれとして流しておくためにも笑いがあるのかもしれません…。笑いの難しさについて皆さんはどのように感じるでしょうか?
テレワークになってからは、同僚や部下、上司ととのコミュニケーションを取ることが大切にされており、定期的にMicrosoftのTeamsを利用して会話をする時間が設けられています。しかし、その会話が単に表面的なコミュニケーションに終わっていることはないでしょうか?冗談を言い合って、お互いに当たり障りのないことを言い合って時間を過ごす。笑いもあり柔らかい雰囲気を作ることはチームビルディングに大切なこと。確かにその通りですがが、真のコミュニケーションは、お互いに考えていることを正直に伝えあうこと。もっとお互いに本音で語り合う場が大切ではないかと思います。そうでなければ、ただ表面的にコミュニケーションを取っています、というだけの無駄な時間になってしまう恐れがあるかもしれません。
街中で立ち寄るコンビニで出会う土方の親方風の男性。同僚と会話する時の元気の良さ、明確な話し方。大きな声。何と分かりやすい。きっと日本人が~、日本語が~というステレオタイプの見方は誤っており、自分自身がいる環境で見聞きするもので語ってしまっている。
時として、曖昧さが生み出すプラスの副産物だってあるかもしれません。あらゆる方法に出会い、経験し、試しながら失敗と成功を味わい、それを自分自身のスキルとして身に付けるチャンスとしたいものです。