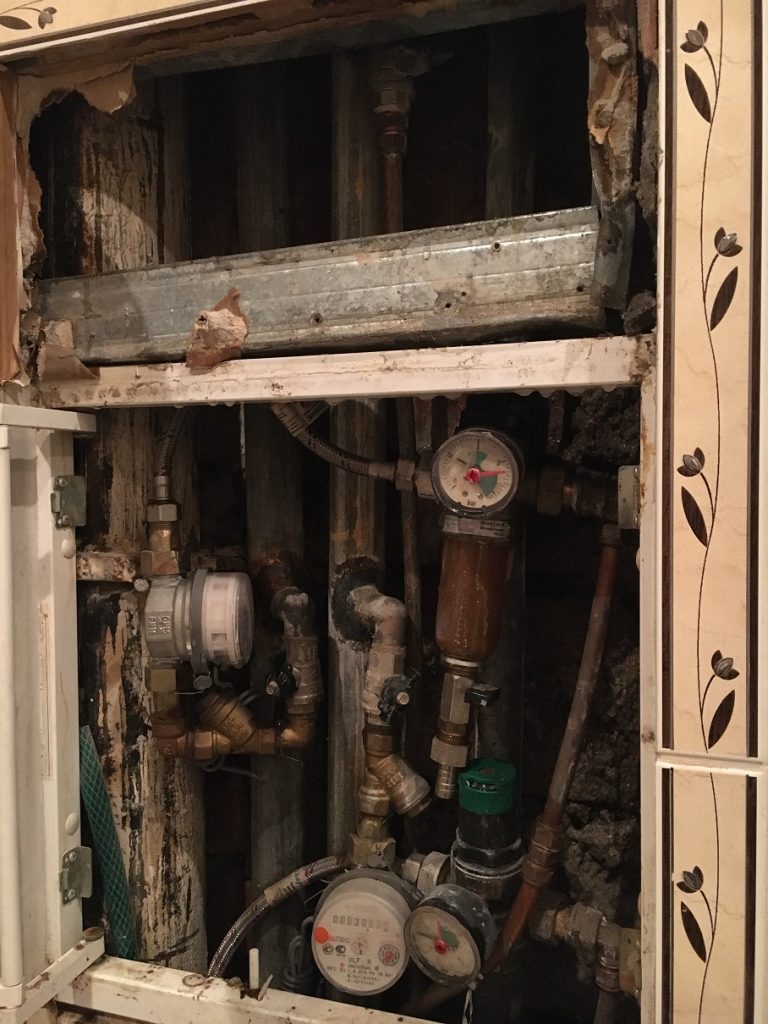そもそも、日本人~ではありません、というタイトル。これこそステレオタイプでよくありませんね…。言えることは、偶然に自分自身がそのような人に多く出会うことでその国の評価を悪く言うも、良い出会いが重なってその国のことを良く伝えることも自分次第ということ。決して自分の体験したことで全体を判断してしまうことは避けたいところです。
さて、すでに2020年も10月ですが、今年1月に約1週間の短い日本旅行で遭遇した、これはないよね…と感じたことを書いています。
当時はまだモスクワ勤務でしたので、約1年半ぶりに日本に”一時帰国”したわけですが、新鮮な目で自分の生まれ育った国を観察できた休暇となりました。おもてなしの国、と言われる日本でありながら、まったくもってそんなことがない。一番の問題点は、おもてなしが形式的であって、そこに心がこもっていないケースに出会うことが多かったこと。そして想定されるマニュアルから外れるやり取りが生じると、そこに何となく嫌な雰囲気が生じる(顔や態度、声にその方の本質が出てくる)ことも。だからこそ形としておもてなしを示してくれてはいても、それが本質的ではないものを感じ取る場面に幾度も接すると、一体この国が言う”おもてなし”とは一体なんなのだ?と思ってしまうわけです。
数年前、日系航空会社が無料で行っているという「日本のおもてなしセミナー」をロシア人スタッフのために開いていただきました。例えばお辞儀の角度の違い、日本で買い物をすると袋の上を留めるテープの端はテープの内側に織り込んで留めることで、お客様が後で簡単にテープをはがすことができる、そんな日本の礼儀作法の説明があったことを覚えています。
もしかすると、日本は”おもてなしの国”と強調しているものですから、このおもてなしの精神をどの場面においても期待して(そんなことはあるはずがないのに)、その期待を裏切られた気持ちになりがっかりし、残念な気持ちを過度に味わうのかもしれません。一方、日本語を理解しない外国人にとっては、目に見える形でのお辞儀や袋のテープ、そういった”おもてなし”をもって日本をポジティブに捉える方もいるのかもしれませんね。(ロシア人の友人に聞いた日本の良いところは?で、大体耳にするのは「公共トイレの綺麗さ」でした。あくまで私の交友範囲に限ります)
成田空港:パスポートコントロールのところで交通整理をしているおじいさん。日本国籍と外国籍とで進む窓口が異なりますが、私の前のほうには明らかにロシア人と思われる女性が「日本旅券所有者」専用の方向に歩き出しながらも、どちらにいってよいのか悩んでいる様子。それを見たおじいさん「あなたこっちは日本旅券専用だよ、あんた日本のパスポート持っているの、持っていないでしょ、あっちだよ」といいながら手でしっし、というような手振りであっちにゆけと女性に案内しています。国際線の到着側で働くのであれば、せめて簡単な英単語を少しだけ覚える。笑顔と腕の動きで”あなたはあっちですよ”と示す。そんな程度で十分におもてなしになる。それにしてもあの態度には驚きました。
フジテレビの展望店のレジにて:自分の思っていること以外のことが起こったときに違う人柄が出てるくるというか…逆にこちらが驚いてしまった。ロシア人の友人が購入するものを選び終え、レジで支払いの際クレジットカードをトレーに提示したのですが、そこで時間が経過する中でバッグや店内を見渡して目を離している間に支払いを終えたと勘違いしてしまったようです、どうやら店員がカードの支払い処理を済ませる前に財布にカードを商品の入った袋をとってレジをあとにしようとしました。私もその後ろに並んでいたのですが、他の友人と会話をしていてよく見ておらず。とすると、先ほどまで淡々とレジ作業をこなしていた女性。目の玉が飛び出るかのような非常事態の顔で、「お客さん、お金払ってないよ。Pay money, pay money!」と大きな声で騒ぎました。こちらも一体何事かと驚き振り返りました。その友人も状況を理解し、カードを再提示して支払いを終えることができました。
この場合に限ったことではなく、レジスタッフの業務を見て感じるのは、レジの作業には一定の流れがあるようです。いらっしゃいませ、商品お預かりいたします、お支払い方法は?ポイントカードはありますか?ありがとうございました。その流れを少しでも乱すような作業が入ると、あたかもお客さんが敵であるかのような怪訝な顔。おもてなしの精神がない形骸化した接客業。それであれば、マニュアル化が必ずしもされていないロシアで時として出会う素晴らしい接客。こちらも決して期待をしているわけではないので、良い接客に出会うとよい印象が強く残るのかもしれません。モスクワの店員の接客は、今日は機嫌が悪そうだな、と様子がよく伝わってきます。ずっと自然で、笑顔もありますし、こちらがむにゃむにゃ自身が無さそうに会話すると「もう一度いってください」と怪訝な顔をする、でも伝われば笑顔になる。そう、自然。おもてなしの精神も礼儀やマニュアルがあり、それを土台として対面する相手に合わせた応対をすること。それがまず原則のはずです。
おじいちゃん、それはないでしょう:エスカレータで一方の側に立っている人にぶつかっても何も言わずにエスカレーターを降りてゆく。それはないでしょう。きっとその人の問題でしょうが、ふと、日本では、お年寄りでずいぶんとひどい振舞いの人が増えている、とどこかで読んだ記事を思い出してしまいました。お年寄りの絶対数が増えているので、そのようなケースが増えてゆくのは必然ではないでしょうか。
浅草の売店:創業百年以上の小さなお土産店でしたが、そんなお店の中で、「部長、社長から電話です」こんな小さな従業員がいないであろうお店でこんなタイトルでのやり取りがあるのかあ、と。それはよいとしても、この部長である高齢の女性の接客がひどいこと。お客をさばいている、早く買って帰ってちょうだいね、といった様相があからさまに感じ取れました。
ロシア人の友人がしばらく時間をかけて孫への着物を選んでいました。その間に彼女が商品を包んでレジのそばにおいておきました。その間にその方が着物を紙に包んでくれました。ようやく会計です。時間が経過していることもあり友人がレジにやってきて何を購入したかもう一度再確認したがっています。部長さんは紙包みの上に色をかいてくれていましたが、私は本人に商品をもう一度見てもらうほうが確実で安心できると思い、「もう一度商品を見せてもらえますか?」とお願いすると、あからさまに嫌な顔をして「創業百年以上ですから。信頼してください」と。それでも包みを開いてくれましたので感謝ですが、ただ一つテープをとるだけです。それに、私は色を確認したく、友人にも今一度確認してもらおうとの気持ちからであり、お店の商品の質などを信頼していないわけではないのですが…。自分自身の思った通りに物事がすすまないときに余計なことにピリピリしている様子がはっきりと見て取れる。これで接客業かぁ…と。もちろん、毎日ありとあらゆるタイプのお客さんが来るのでいつも良い客ばかりではないはずですので、面倒だな、と感じることもあるのでしょうが、それを言っていたら接客業は務まらないのではないでしょうか。
芦ノ湖の売店にて:レジのカウンターにアジア系(おそらく中国か韓国の方)購入客が置いた荷物を邪魔な様子で手の甲でどかす。その人の態度にはどこかしら中国人や韓国人のお客さんに対する見下したような様子を感じてなりませんでした。そして、「このレジ間もなく終了します。買い物をお済ませでないお客様はお早めに会計をお済ませください!」店内に日本語で大きな声でアナウンスしています。そんなこと日本語で、どれだけ大きな声で言ってもその場にいる外国人に伝わるでしょうか?芦ノ湖には日本人だけではない外国からの観光客が来ているのですから…
小田原行きのバス運転手対応がひどい:ロシア人の友人たちを芦ノ湖の宿へ送ってお別れ。そこから私は滞在する実家に向けて帰路につきました。小田原駅に向かうバスが到着。口をあけたままの牛乳パックを手にもって乗り込もうとすると、「お客さん、それをもったまま乗ってもらっては困ります。それを持っては乗車できません」と、ぶっきらぼうな態度。その場で処分して乗り込みました。小田原駅で降車の際、支払い方がよくわからず、お札をどうしてよいのか少しの間試行錯誤していたら、お札はこちらね、といってお札専用の入れ口を示してくれました。そんなこと最初から言ってくれてもよいのでは、と内心思いつつ、「あ~すみません・・ありがとうございます」と。彼もその日は仕事でお疲れだったのかもしれませんね。日本の友人に話すと「う~ん、バスの運転手だったらありえるかな、運転手はあまりよくないよね」とのことでした。これもステレオタイプですよね。確かに蓋のついていない飲料を車内に持ち込むことはよくなかったかもしれません。