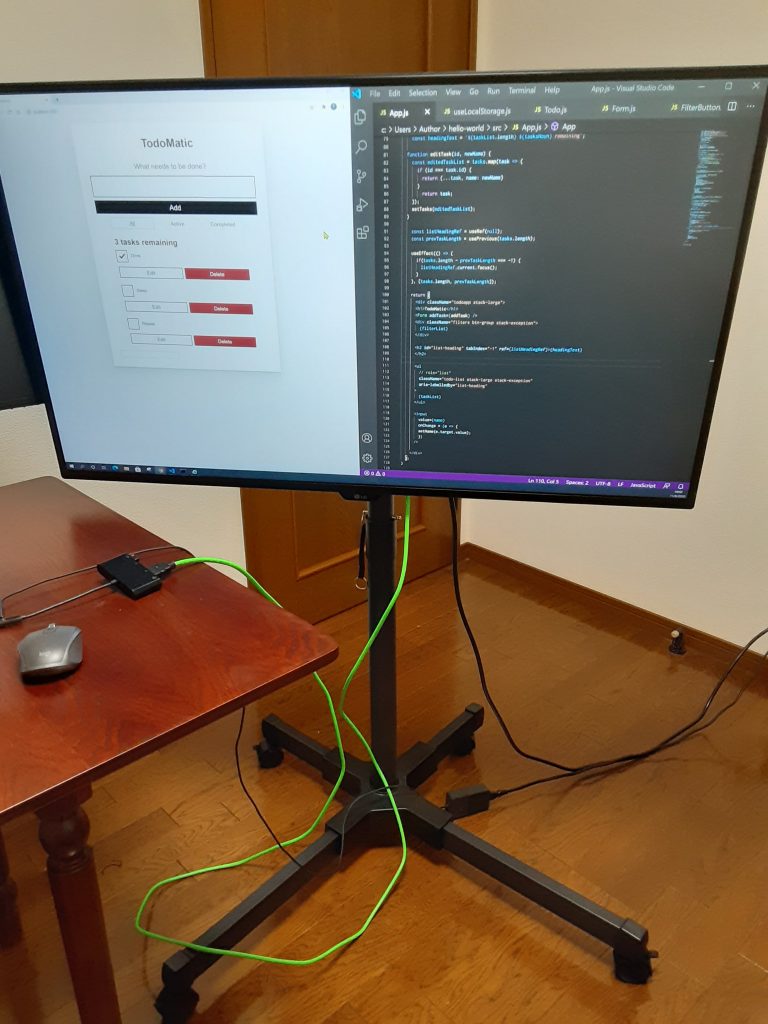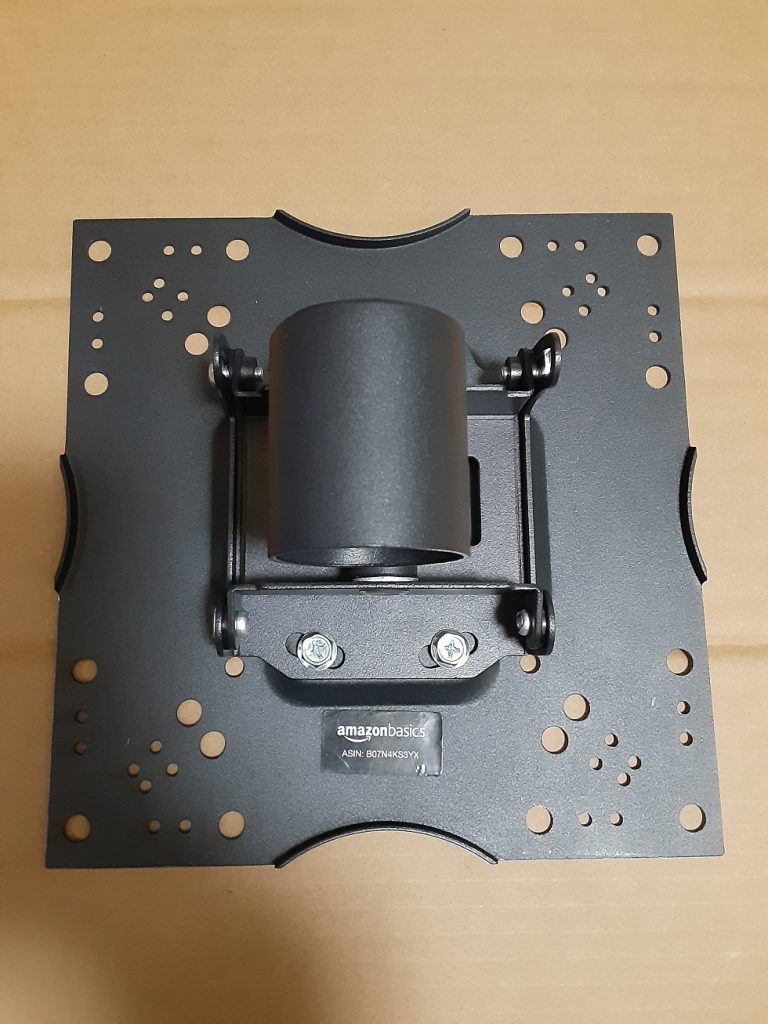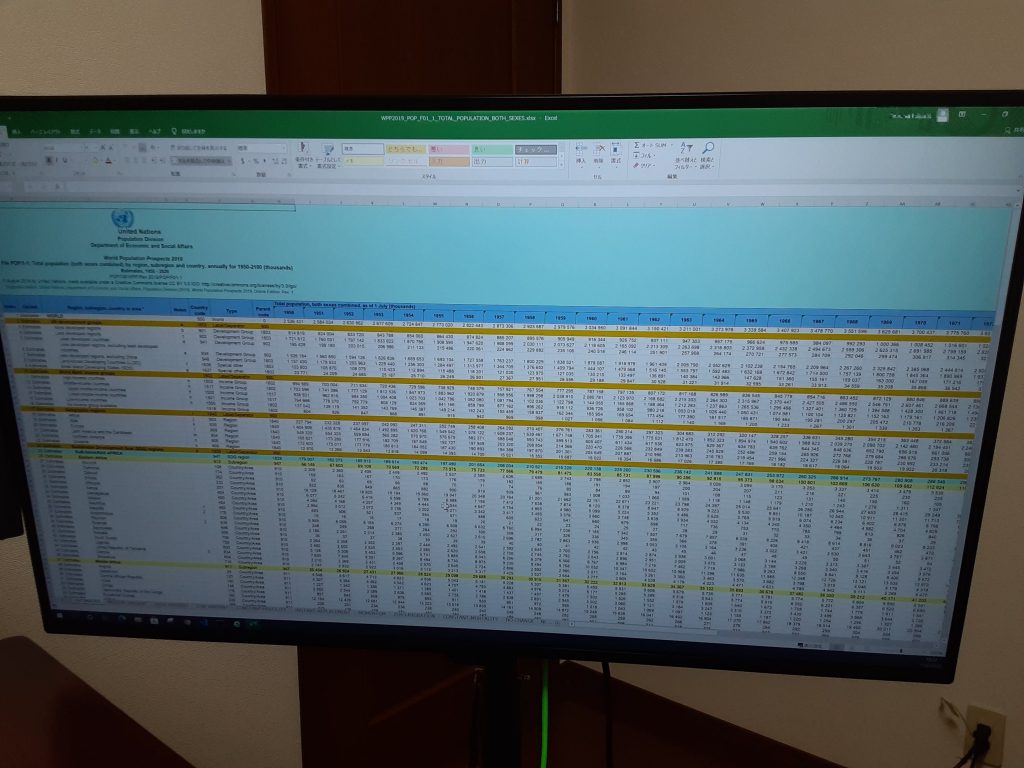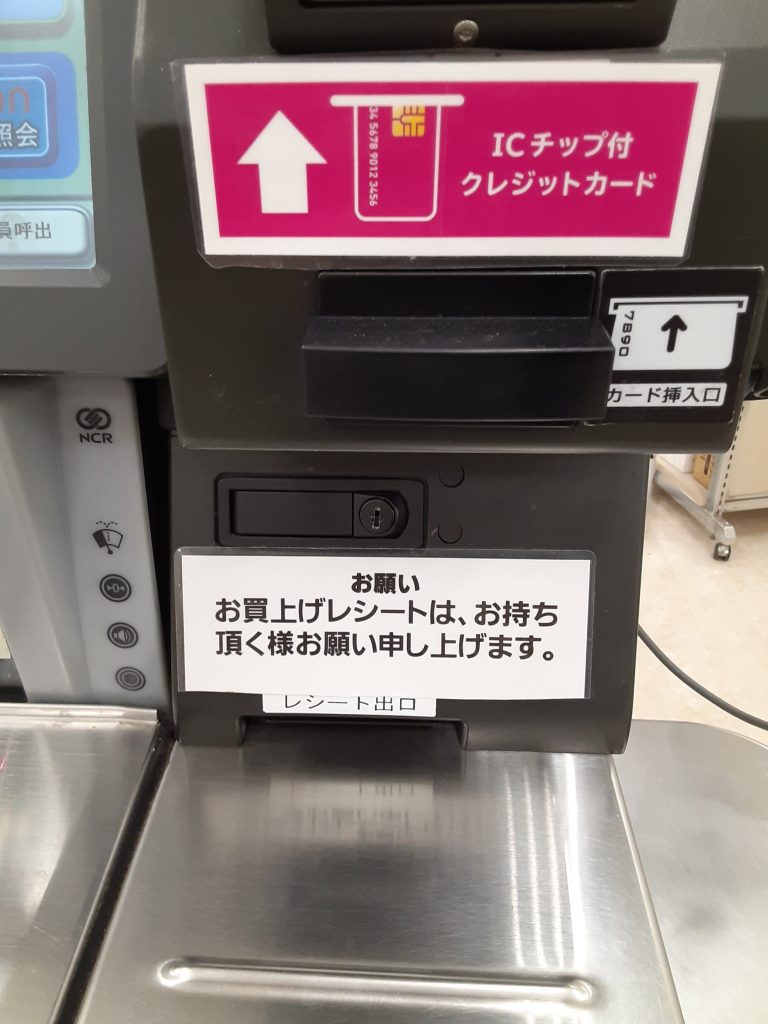モスクワの駐在生活でしか経験できない醍醐味の一つは、日本には存在しないモスクワの歴史的なアパートに住むことができる、という点があります。有名なスターリン様式のアパートはまさに他の国では見ることができません。都心の中心部ということで家賃も高く、自分の負担で住むとなると難しいところを会社の補助があるからこそ選択肢に含めることができます。モスクワ駐在の際には歴史的なアパートを検討してみることをぜひお勧めします。ロシアのモスクワ以外の国に居住したことがないので、他の国ではどのような物件があるのかは分かりません。ドイツに駐在していた友人の家や他の西欧の国々を訪れたときに見たアパートは、日本のものとは異なりますが、急に日本から引っ越したとしてもあまり違和感のない雰囲気であった気がします。日本のこれまでの生活で、よく目にした映像や似たような雰囲気のものを実際に生活で経験しているからかもしれません。
今のモスクワでも現代的なアパートが立っており、現地に住む友人曰く、いまではロシア人でもそういったアパートを好む層が増えているようです。Youtubeでみる現代的なアパートは、現代の生活に適している、内装もシンプルなものが多い印象です。部屋の中を紹介するRoomTourビデオをYoutubeで見るのが好きですが、予算に制約があって、それでも部屋の中をオシャレにデザインしたい人はIKEAを好んで購入しているように感じます。
歴史的なアパートを好き好んで選ぶ人は徐々に少数派になってくるのでしょうか。確かに歴史があっても水回りや部屋の造り、古い電気設備など、古いアパートを好む理由はあまりないでしょう。
Архитектурные излишества
(辞書によれば意味は「建築の装飾過剰」。この名称を付けた背景は分かっていません)
https://www.youtube.com/channel/UCrBrH2HVtIA6-kk42E5m7yw
Youtubeで見つけたこのサイトはおすすめです。モスクワに住んでいて、ここは一体どんな住み心地なのだろうか、と建物を見上げては想っていた建物がまさに紹介されています。全てロシア語ですが、モスクワの街並みやアパート内部の様子、雰囲気がこちらにも伝わってくる、とても綺麗な映像が並んでいます。
例えばこんなアパート。日本では決して見ることができない外観と内部の雰囲気。そして窓から眺める風景。モスクワの中心部に関して言えば、赤の広場を中心に古い建造物が広がっている街並みの景観は一度は経験してみたいものです。
私は7年間のモスクワ生活のうち、3つのアパートを経験しましたが、どうしても仕事柄オフィスに近いところを選ばざるをえませんでした。その理由は不測の事態があるときにはすぐにオフィスに駆け付けられるように、生活の大半が仕事で占められていたためにオフィスへの移動を徒歩圏内にしたかったことです。モスクワの大渋滞は半端ないです。同じように渋滞がひどいと聞く東南アジアを経験しておらず比較できませんが、モスクワはあれだけ多くの車線があり、あれだけ大きな道があるにも関わらず、時間帯によってわずか1km程度を車で通過するのに1時間近くかかったこともありました。冬にもなると、オフィスへの通勤のために片道2時間もかかっている駐在員もいましたので車での移動がいかに恐ろしいものか想像していただけるのではないかなぁと。
きっと次にモスクワに住むことになればじっくりと考えてアパートを選ぶでしょう。最後に住んだアパートは、限られた選択肢の中から1930年に著名な建築家によって設計されたという由緒ある建造物を選び移り住みました。数か月前から物件情報を眺めて気になっていたのですが、しばらく経つと提示価額が下がったことをきっかけに紹介元にコンタクト。そこからスムーズに手続きも進み無事に決定です。建物はスターリン様式のようなもので(Wikipediaによれば、当時世界最大のビルとなる計画であったソビエト宮殿(スターリン死後に計画中止)の最終デザインが固まった年1933年からソビエト建築アカデミーが廃止された1955年の間に建てられた建物をスターリン様式というようです)天井は高く、外観と窓から眺める夕日は最高のものでした。違うアパートにゆけば、そこで見つける新たな最高の景観があるはずなので、終わりの無いテーマですね。オーナーの父親は日本に行ったことがあってとても日本が好きだ、というオーナー。アパート選びにはオーナーがどんな人かも非常に重要なポイントです。
今回紹介したYoutubeでは、モスクワ以外の町も紹介されていて、モスクワとは違う様子も楽しむことができます。そのうちのいくつかは私も休みを利用して出かけたことがあります。早朝にモスクワを列車で出発し2,3時間の距離にある町を散策して夜にはモスクワに戻ってくる。モスクワでの慌ただしい生活を離れて、ゆっくりとした時間が流れる違ったロシアを知ることもまた駐在していたあの日々の醍醐味でした。