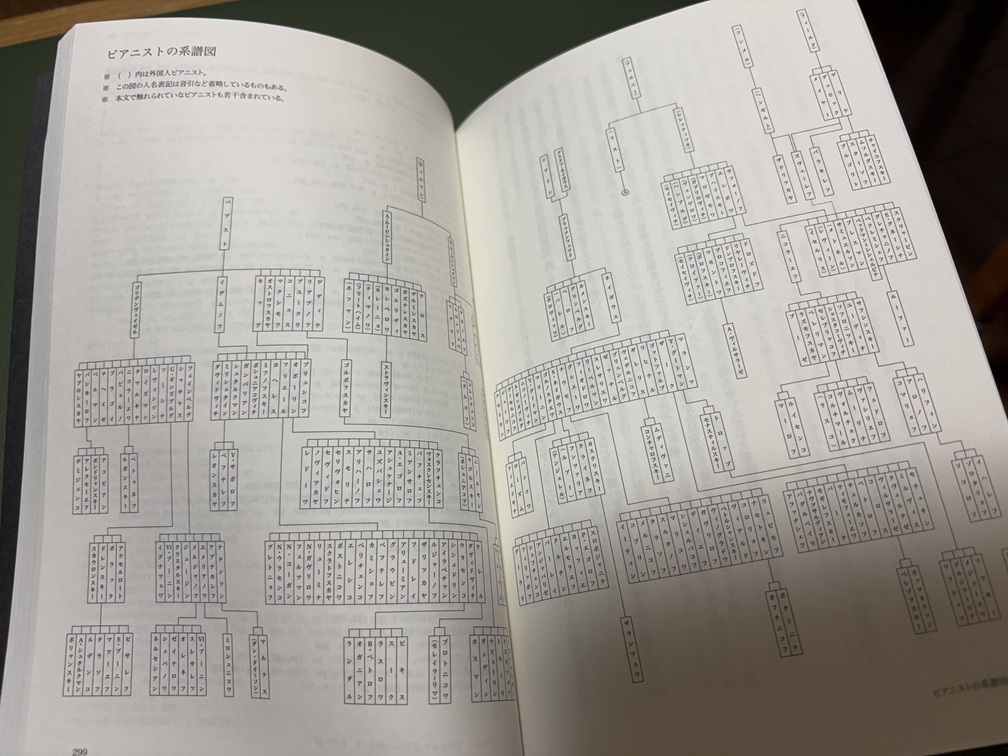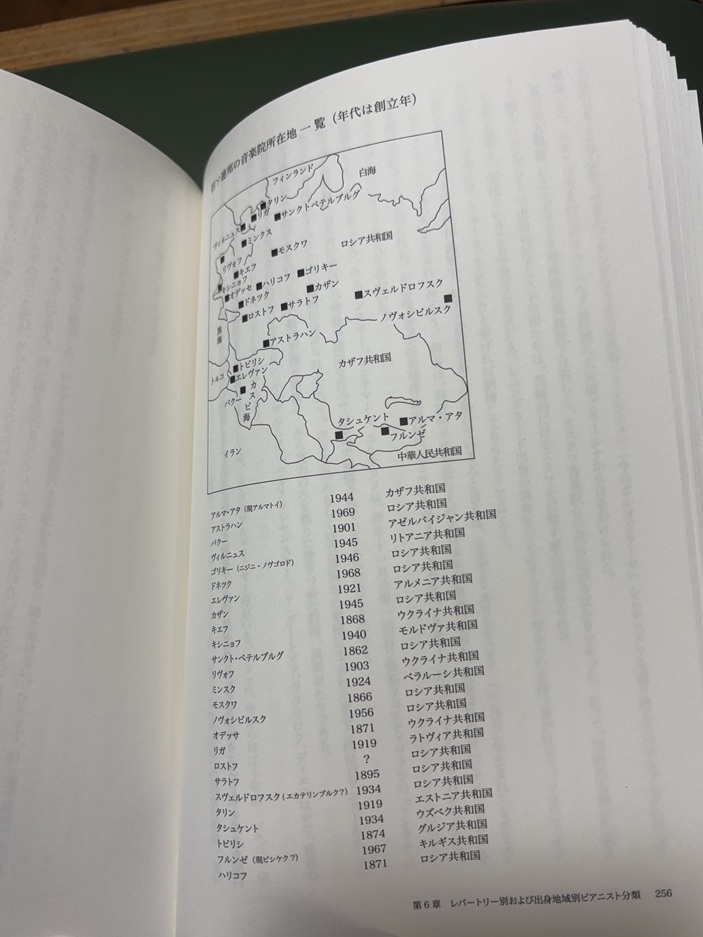Duolingo学習を始めて950日。実のところ、この950日達成したと言っても途中で幾度か記録が途絶えていることがあります。まずい、Duolingoを今日まだやっていなかった!でも気がついたら時計が24時を回って日付が変わっていたり。その日一日は仕事だったりプライベートで他のことに意識を取られてしまい何もせずに終わってしまったり。そんな時、Duolingoには連続記録を途絶えさせないためのオプションがあります。それに助けられて形式上は950日連続記録が続いていますが、その間には記録更新が実際には途絶えてしまったこともある、というのが事実です。また、語学学習について言えば、ここ最近は新たにサービスが始まった算数やチェスをプレイすることも多く、ロシア語の学習をDuolingoで行うことはほとんど無い時期もありました。
ここ最近Duolingoのロシア語コースを改めてチェックしてみると、とても良い機能が備わっているなと感じて、ロシア語の勉強をDuolingoでも再開しました(本来備わっていた機能であってそれに私が気が付いていなかっただけであればご容赦ください。)それは自分の音声を取り込んでテキストに書き起こしてくれるものです。自分の発音レベルも分かりますし実際に話す練習にもなるのかなと思います。動画で撮ってみるとこんな感じ。Duolingoが認識してくれる発音レベルが優しくなってるのではないかなと思ったりしますが(自分で間違っているな、と思ってもDuolingoが正しいスペルで書き起こしてくれているように思えることがチラホラと)概ね正しく文字起こしをしてくれています。
白紙状態のところから自分の音声でロシア語文章を吹き込むこと、これを毎日続けるだけでもスキルアップになるような気がしてます。
さて、10月から11月にかけてロシアから友人が日本に来ていて久しぶりの再会を満喫してきました。仕事もあるので彼らとずっと過ごすことはできず、11月頭の3連休を一緒に過ごし、その翌週末の日本滞在最終日には再び彼らと合流して東京駅散策→成田空港での見送りをしてお別れとなりました。この時間で多くのことを学びました。道案内、レストランでの食事で和食や日本文化の説明をしようとする時に自分のロシア語スキルの至らなさを痛感する経験。そこから自分は何が出来て何が出来ていないのかを把握できる。この日本語をロシア語で表現するとどのように言い換えて表現したらよいのだろう?と熟考する経験。それが日露通訳スキルアップのための訓練になる。
言葉っていうのは生きているので、あらゆる形になって姿かたちを表す。時と共に変わっていくだろうし、教科書にはこう書かれているけど、今の時代にはロシアではそんな風に使われていない、なんてこともあるに違いない。生きたロシア語に触れることで何かこう鮮明に自分自身の課題を認識することができた時間。それは決して甘いものではなく苦い味のする終わりのない新たな長い長い道のりが見えた時間だったけど、やっぱり言語って面白い!という気持ちを改めて感じるものでした。
以前の記事でも書いているけれど、Duolingoだけではハイレベルな言語習得は難しいと思う。それでも、自分が何日間継続して学習できているかが可視化されること。何よりもちょっとした時間を利用して、世界中の人たちと順位を競いながら楽しく学習できること。そんなDuolingoも併用しながら勉強を続けていくとモチベーションも保ちやすくなるのかな、と今はそう思っています。